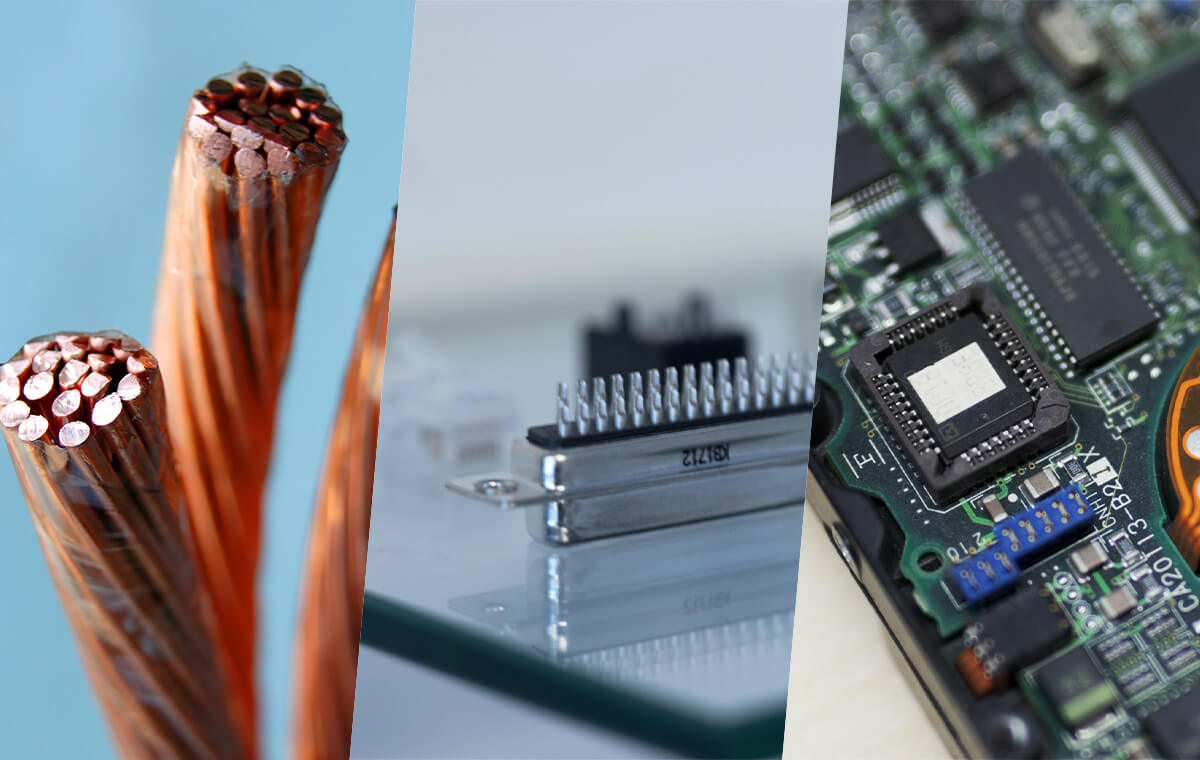日本の近代化を支え、屈指の電線使用量を誇る造船業界

日本は幕末から明治にかけて西洋の技術や知識を吸収して、製鉄、造船、石炭産業といった重工業の発展を推し進め、約50年という類まれなスピードで欧米列強と肩を並べるまでの近代化を成し遂げました。
なかでも造船業は第二次世界大戦後も日本の復興を支え、昭和31年(1956年)には進水量において英国を抜いて世界一の造船国となり、その後60年以上に渡って造船大国として世界中に船を供給し続けています。
船はそのサイズや用途にもよりますが大きいものでは300mを超え、高層ビルを横倒しにしたような巨大な可動建造物で、富士電工の礎でもある電線の使用量は1隻あたりで30万mを超えるものもあります。販売先としてはこれ以上ない使用量を誇る業界ですが、70年の歴史を持つ富士電工も造船業界との取引はこれまで経験がありませんでした。
きっかけは既存顧客からの相談
入社2年目の夏、普段通りに既存のお客様のところへ向かい、納期や伝票などの業務話をしている最中、一つの質問を受けました。
「良い舶用電線のメーカーを知らないか?」
そのお客様は船舶用の発電機や配電盤を製造しているメーカーで、話を聞いたところ現在使っている船舶用電線の品質が良くないということでした。韓国のメーカーを使用しているがこのところ不具合続きで、かといって日本のメーカーは価格が高いから困っているという内容です。
その場では持ち帰って検討しますと返答しましたが、社内で聞いても舶用電線について詳しい人はいませんでした。
ちょうどその時期、富士電工の購買部が中国へ新規仕入先の開拓へ行くという事で、担当者に良い舶用電線のメーカーを探す依頼をし、実際に訪問してきてもらいました。帰社後にその企業のパンフレットを見たところしっかりとした会社の様で、早速お客様に紹介することに。
電線の見積を提出したところ、「価格は安いが船級規格を持っているか?日本への実績はあるか?」との指摘を受け、その時初めて船舶業界への参入へのハードルの高さを知ったのでした。その後も採用までに超えるべき障壁の多さを知るにつれ、このビジネスの成功確度が低いことを思い知らされました。
造船所への挑戦
不振に終わった舶用電線の販売でしたが、諦めきれず業務の合間を縫って船舶業界の情報を調べ続けました。ほとんどの造船所が韓国製電線を使っていること、中国製を使っている企業は1社もないこと、各造船所の規模や特徴、造船に必要な規格など。
船は人を乗せて安全に運ぶという使命があるため、そこに使う電線などの品質には厳格な基準が設けられています。わからないことは国土交通省や日本海事協会に何度も足を運び、自分の中の疑問を解決していきました。
別件での中国出張に合わせて実際に中国舶用電線メーカーへの訪問も果たし、「この会社の電線は売れる」という自信を深めた結果、本丸である造船所へ電線を販売したいという思いが強まっていったのです。




富士電工には「前例にとらわれず様々なことに果敢にチャレンジする」という企業風土があるため、上司に造船所への訪問を相談したところ快く承諾をもらうことができました。
三菱重工業様の採用―東京湾を彩る3代目さるびあ丸への納入
造船所へのツテがない中、事前に台本を作成し、ホームページから直接電話をかける戦略をとることにしました。最初の訪問先は日本造船業の祖である三菱重工業様で、緊張しながらも担当者につないでもらい、訪問のアポイントを取り付けることができました。

事前に多くの時間をかけて勉強をしていた甲斐あって、先方の疑問点に滞りなく答えることで信用を得ることができ、初訪問にも関わらず数千万円の金額に達する見積依頼をいただくことができました。
そこから価格の調整やサンプルの評価、中国へ招待しての現地工場監査など、3年余りの時間をかけて課題をクリアしていき、2018年に初めて本土⇔離島間の高速船への採用を頂くことが決まりました。
そして2019年、富士電工の本社からほど近い、竹芝に本社を構える東海汽船様の「さるびあ丸(3代目)」に、1隻丸ごとに近い量の電線を納入することができました。
さるびあ丸は船体のデザインを東京オリンピックのエンブレムを手がけた野老朝雄氏が担当したもので、“本船のコンセプトである「本土と島を繋ぐ」ことをイメージした幾何学的な波模様を、伊豆諸島の海に映える藍色で船体に表現”されている船です。

ここへ至るまで数えきれないほどの壁にぶつかり「今度こそダメだ」という思いを味わいましたが、その度に過去の経験を思い出し、「あの時乗り越えたんだから今回も乗り越えられる」と自分を奮い立たせることで、造船業界への新規参入というかけがえのない経験をさせていただきました。
また、お客様である三菱重工様や仕入先メーカーを始め、多くの人に協力をいただきながら進めたプロジェクトが成就した際は、営業としても何事にも代えがたい喜びを得ることができました。これからも新しい事へのチャレンジを続け、後進と共に多くの人に喜んでもらえる仕事をしてきたいと思っています。